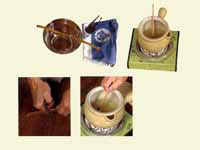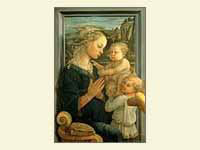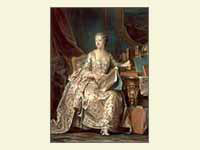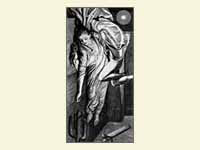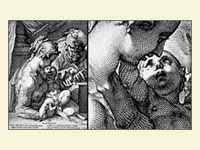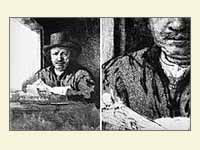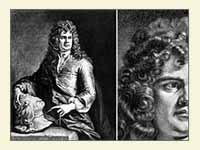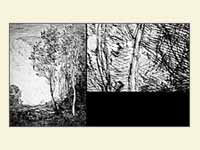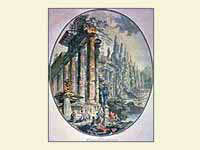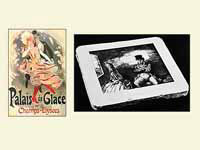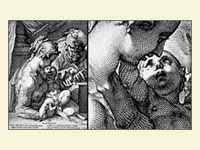
|
●エングレービング(凹版直刻法)
ビュランと呼ばれる鋭い刃物(ノミ)で彫り、まくれは、スクレーパーで取り除く
細く明確な線が特徴
ヘンドリック・ホルツィウス 「聖家族」 1580〜1890年 パリ国立図書館
右/拡大図斜線やその交差、その交差部分などで微妙な陰影を作り出している |
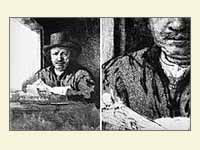
|
●ドライポイント(凹版直刻法)
先端が鋭く尖った鋼鉄の針(ニードル)やナイフでじかに版に傷つけ、金属の削りかすやまくれはそのままにされる
レンブラント 「デッサンするレンブランド」 1648年 パリ国立図書館
右/鉄筆できる「まくれ」にインクが溜まり、線に「にじみ」ができる それが、表現にニュアンスを与える |
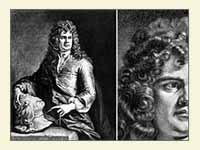
|
●メゾチント(凹版直刻法)
フランス語で、「黒の技法」と呼ばれ、版面全体をノコギリ状のロッカーと呼ばれるもので、細かい傷を付け、凸の部分をつぶして図柄を作る
微妙な明暗の変化が得られる
ジョン・スミス「グリンリン・ギボンズの肖像 18世紀 パリ国立図書館
右/縦横斜めにつけられた凹みによる暗部から白い明部をつくりだしてゆくのがメゾティントの特徴 |
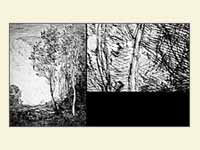
|
●エッチング(腐食法)
金属板をグランドで覆い、ニードル(針)で描画し、希硝酸の液につける
表面の一部を選択的に科学的、電気化学的に溶解する加工法
カミーユ・コロー 「イタリアの想い出」 1866年 パリ国立図書館
右/防食性の被膜の上から鉄筆でひっかく強さや腐食の回数によって線の強弱、太細が得られる |
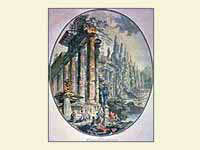
|
●アクアチント(腐食法)
版面に樹脂の粉をふり、熱を加えて定着させ、不必要な部分をワニス等で防食しておいて、腐食液に浸す
粒の隙間だけを酸が侵して版面に梨地の斑点ができ、また水彩のような表現が可能で、水彩画の複製にも用いられた
ジャン・フランソア・ジャニネ 「ローマの廃墟」 1780年 パリ国立図書館
|
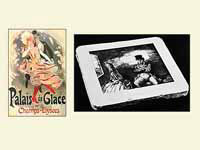
|
●リトグラフ(平板)
大理石や、石灰岩等の石板に溶いた墨や、クレヨンで絵を描き、小刀で削ったり硝酸ゴム液を塗ったりして、油を吸収する部分と反発する部分をつくり、油性インクで印刷する
H・ドミーエ 「鉄道に乗って 快適な隣人」 1862年
J・シェレ 広告ポスター 「氷の宮殿」 1894年 |

|
●シルクスクリーン(孔版)
目の粗い絹布を枠に張り、印刷しない部分を膠や型紙で覆って、その上からゴムローラーでインクを押しだす
インクを厚く盛れるので、色彩、画線が強調される
各自の点字印刷にも用いられる
「ステンシル」「プリントごっこ」もこの孔版印刷にあたる |

|
●ファイバーアート
タペストリーの枠を越えた作品 |