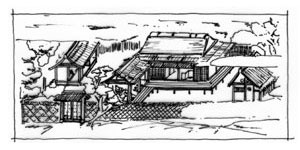|
●二条城
徳川家康が上洛の際の居館として建てた
1788年焼失
現在のは、旧桂宮御殿を移築したもの |

|
●帳台構 (二条城)
上段の脇に取り付けられた
別名「武者隠し」と呼ばれていたが、非常に重い扉のため簡単には開けられないことから「塗篭」が装飾化されたものと考えられている |

|
●金閣寺(北山文化)
正式には鹿苑寺
1950年に放火により消失
1955年再建
14世紀、足利義満が別荘北山殿を建て、死後遺命により夢窓疎石(臨済宗の僧侶)を開山として寺としたのに始まる |

|
●蔀戸
蔀戸は、細かく格子を組んで裏側に板を張り、外または内側に押し上げて開く水平軸の板戸
開いたときは金具で止めていた
写真は金閣寺の一階部分の半蔀戸で、角柱になっているが、寝殿造りの場合は、丸柱になります |

|
●銀閣寺(東山文化)
臨済宗の寺
慈照寺が正式名
15世紀に足利義政の建てた山荘東山殿を遺命により寺とした |

|
●東求堂
東求堂は、四室からなり、その中の四畳半の部屋を同仁斎という

|

|
●東求堂(同仁斎)
「会所」と呼ばれる「書院座敷」で、少し開け放された障子との隙間から、庭が借景となり、掛け軸のようになる
畳の敷詰めに角柱、違棚、付書院をもち、現代和風住宅の起源ともいえる |

|
●卯建
このころ下町では、卯建のあがった民家がみられる
卯建は火事での類焼を防ぐため、隣家との境に高い壁を設け、その上端に小屋根を置いた
「うだつが上がらぬ」とは富裕の家でなければ、卯建をあげられなかった事から転じたといわれる |